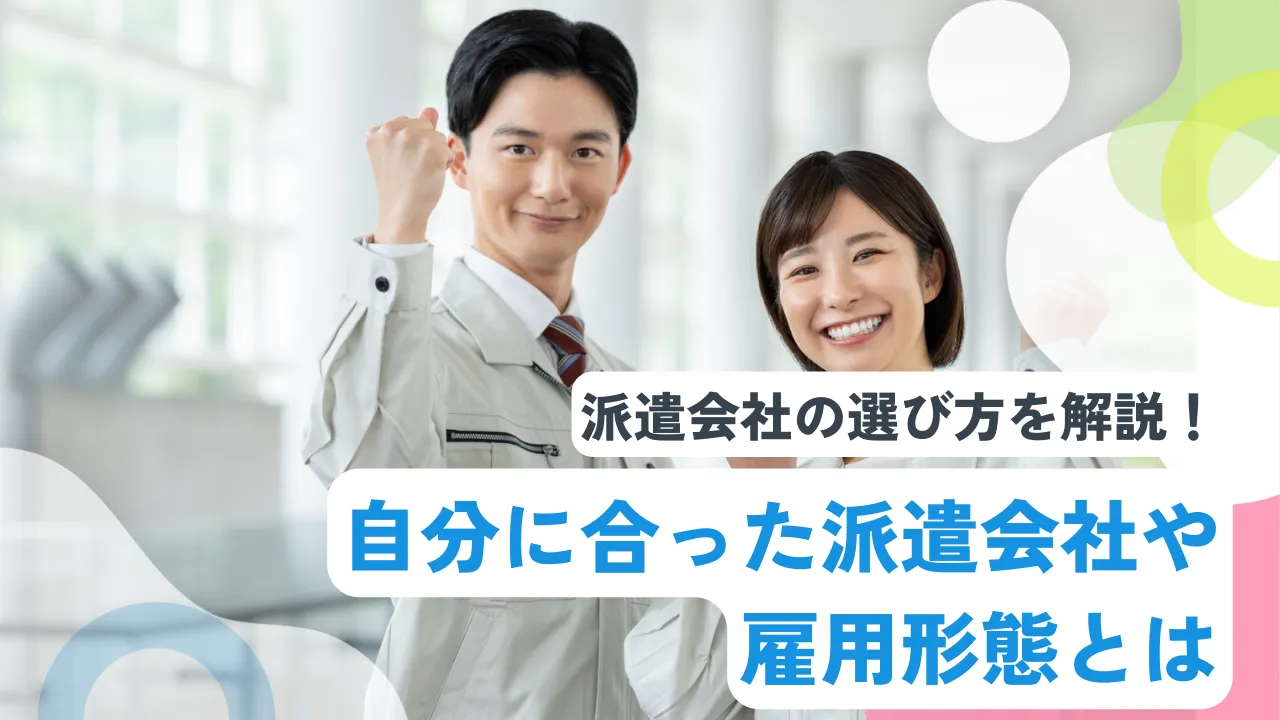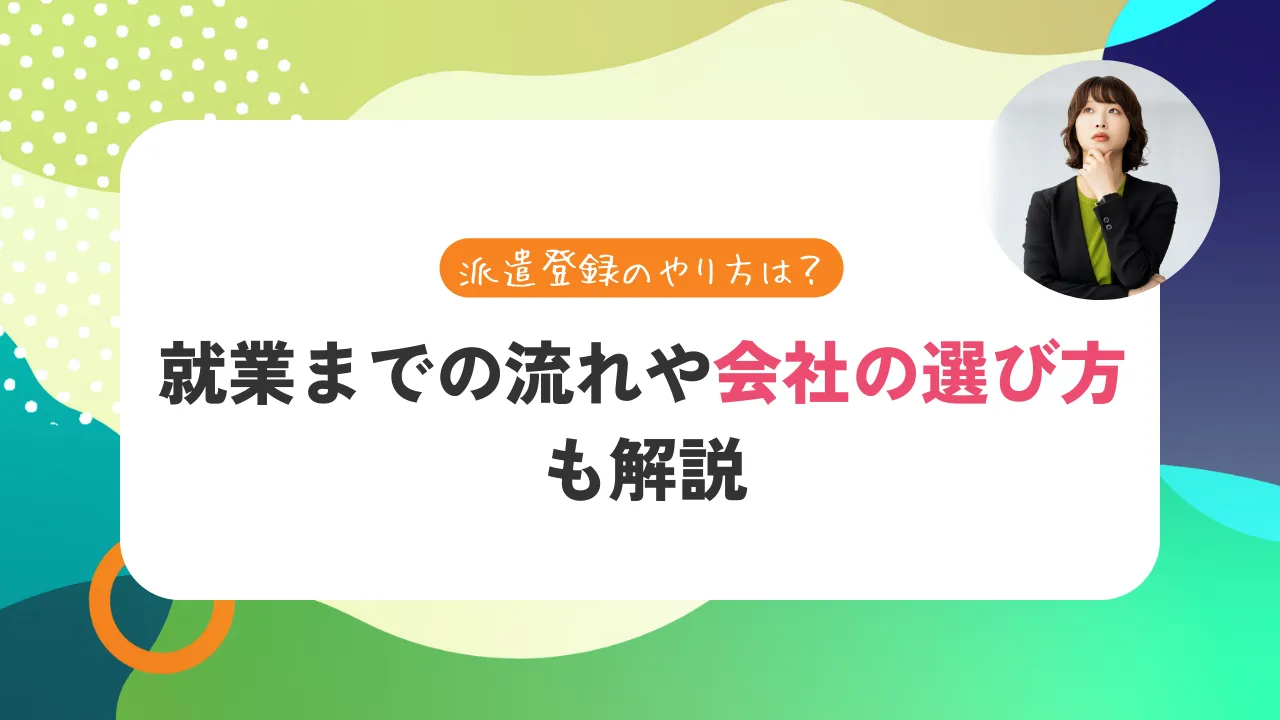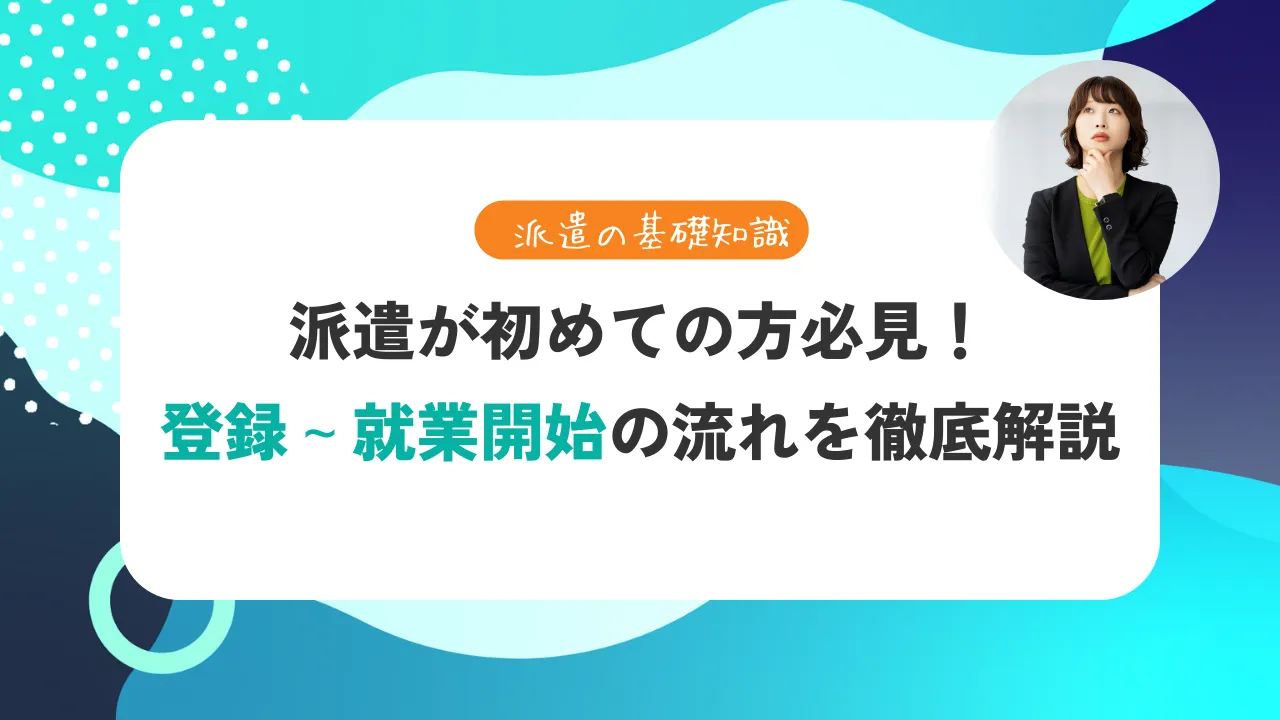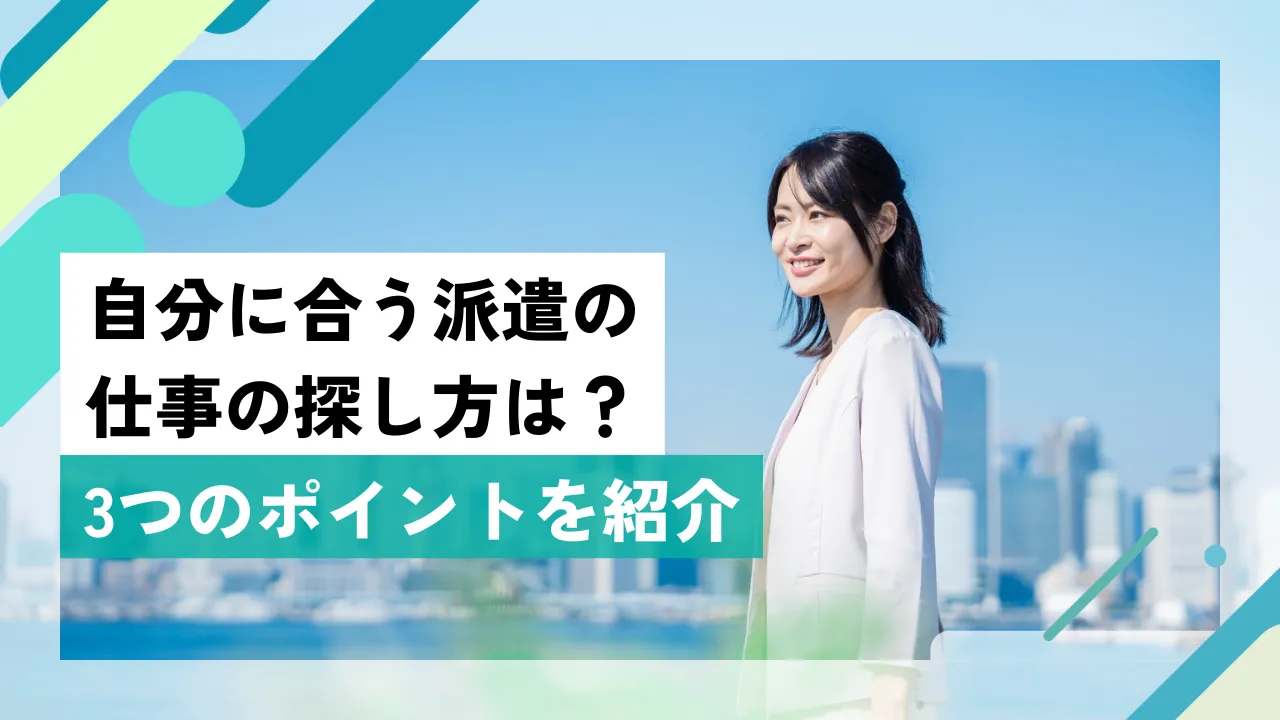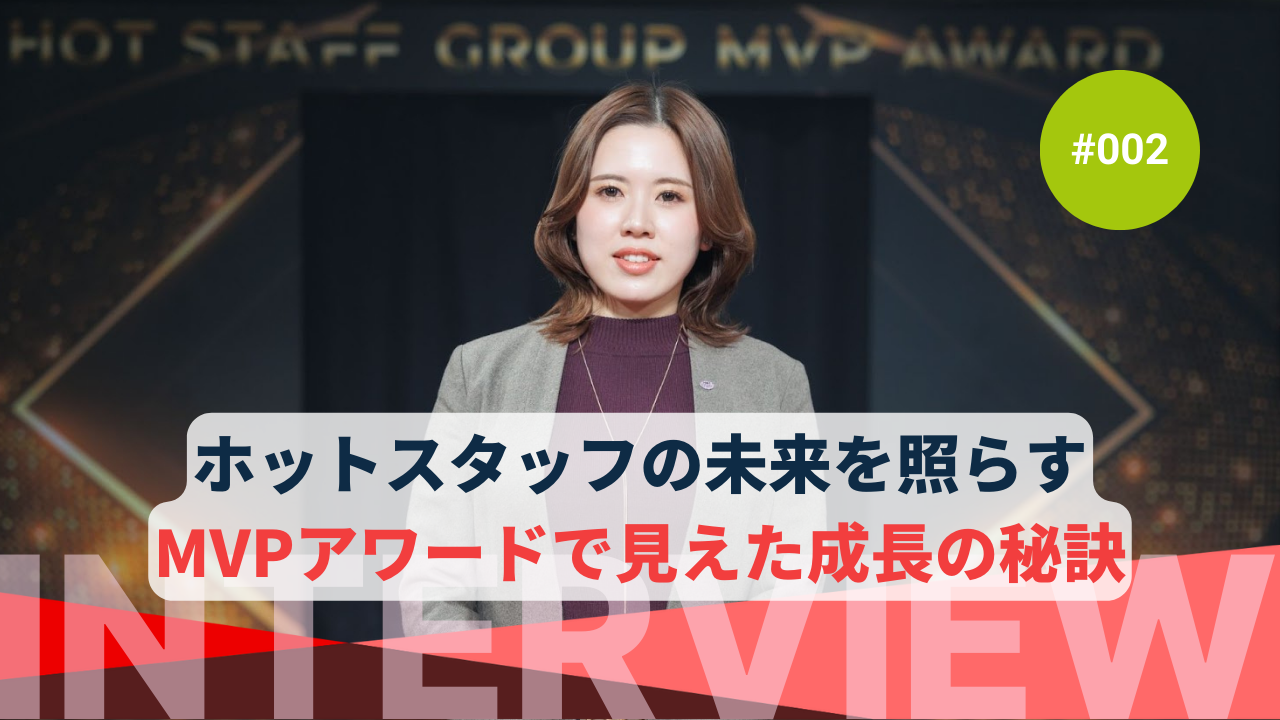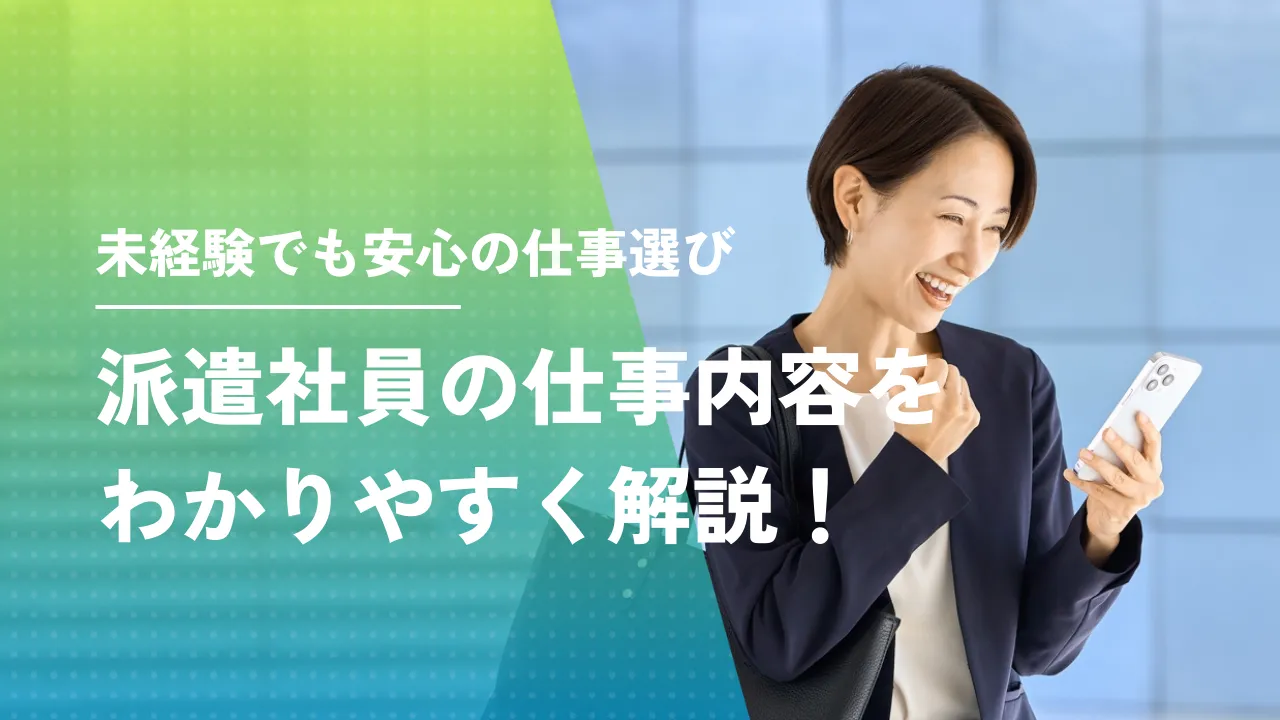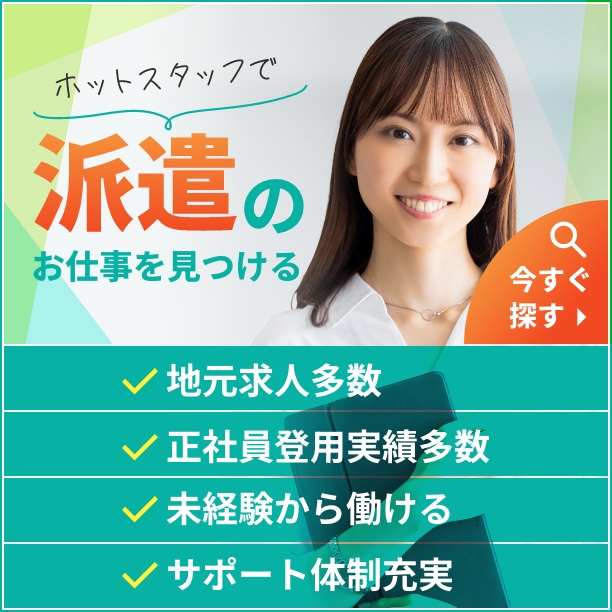派遣社員として働くにあたり、「派遣社員は社会保険に加入できるの?」という疑問をもっている方もいらっしゃるでしょう。
社会保険は安心して働くために重要な制度ですから、派遣社員の場合の扱いについて、きちんと理解を深めておきたいところですよね。
そこで本記事では、社会保険に加入できる条件や必要な手続きを解説します。
「派遣社員として働くための準備を万全に整えたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
社会保険とは
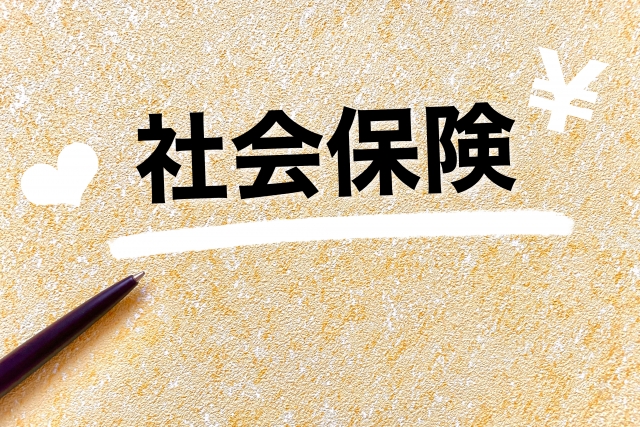
社会保険とは「病気にかかってしまった」「仕事中に負傷した」など、日常で起こりうるさまざまなリスクに備えるための保険制度です。
“社会保険”という1つの保険があるわけではなく、以下に挙げる5つの保険の総称を指します。
社会保険に含まれる5つの保険
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労働者災害補償保険
病気や怪我など、万が一の事態が起きた場合は、加入者が支払っている保険料のなかから、必要な治療費の一部負担や現金の給付を受けられます。
このように社会保険によって、加入者が、加入者とその家族を支え合う仕組みが社会全体で構築されているのです。
派遣社員も社会保険に加入できる?

派遣社員であっても、条件を満たせば社会保険に加入することができます。
むしろ、条件を満たしている場合は、社会保険への加入が義務づけられているため、“加入しなければならない”と捉えておくのがよいでしょう。
社会保険の加入対象者の条件は、以下のように厚生労働省によって定められています。
社会保険の加入対象者
- 週の勤務時間が20時間以上である
- 給与が月額8万8,000円以上である
- 2か月を超えて働く予定がある
- 学生ではない
派遣社員が上記の条件を満たせない例として想定されるのは、登録型派遣で働くケースです。
登録型派遣は、派遣先で仕事があるときにだけ派遣会社と雇用契約が発生する派遣形態で、場合によっては契約期間が1か月のこともあります。
この場合、2か月を超えて契約が更新される見込みがなく、社会保険には加入することができないというわけです。
参照元:厚生労働省
各種保険の概要と加入条件
厚生労働省が掲げる社会保険の加入条件は、前項でお伝えした通りです。
ですが、社会保険に含まれる5種類の保険ごとにさらに細かく見ていくと、対象者や条件が異なる部分があります。
ここからは、保険の種類ごとの概要や加入条件を一つずつ解説していきます。
健康保険
健康保険とは、病気や怪我、出産などの際に十分な医療を受けるために加入する保険です。
健康保険に入っていれば、基本的に医療費の7割は保険による給付が受けられますので、自己負担は3割で済みます。
派遣社員が健康保険に加入するには、以下に挙げる2つのいずれかの条件を満たしている必要があります。
派遣社員が健康保険に加入するための条件①
- 1週間の労働時間と1か月の労働日数が、派遣会社に勤める正社員の3/4以上である
- 2か月を超える雇用の見込みがある
ただし、1週間の労働時間および1か月の労働日数が正社員の3/4未満であったとしても、以下の条件をすべて満たしている場合は健康保険への加入が可能です。
派遣社員が健康保険に加入するための条件②
- 契約で定められた1週間の労働時間が20時間以上である
- 契約期間が2か月を超える、あるいは2か月を超える見込みがある
- 1か月の賃金が8万8,000円以上である
- 勤めている派遣会社の従業員数が51人以上である
- 学生ではない
なお、従業員数が50人以下であっても、派遣社員と派遣会社のあいだで合意がなされていれば健康保険へ加入できます。
参照元:厚生労働省
介護保険
高齢者や特定の疾病を患ってしまった方など、介護が必要な人を支えるための保険が介護保険です。
要介護の状態になった場合は、特別養護老人ホームへの入所や訪問介護、通所介護といった、さまざまな介護サービスを受けられます。
介護保険に加入するには、前提として健康保険の加入条件を満たしており、かつ以下に挙げる各号の被保険者の年齢に該当していなければなりません。
介護保険に加入するための条件
- 第1号被保険者:65歳以上の人
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人
これらの条件から、健康保険に加入している40歳以上の方全員が、介護保険への加入義務があると認識しておくとよいでしょう。
第1号では原因を問わず要介護・要支援の認定を受けたとき、第2号では厚生労働省が定める特定の疾病が原因で同認定を受けたときに、介護サービスを享受できます。
参照元:厚生労働省
厚生年金保険
厚生年金保険は、働いて収入を得ることが困難になったときに備える保険です。
老後に受け取れる“老齢年金”のほかにも、病気や怪我で障がいを抱えてしまったときの“障害年金”、加入者が死亡したときに遺族が受給できる“遺族年金”があります。
厚生年金保険の加入条件は、健康保険の加入条件とほとんど同じです。
一部異なるのは、厚生年金保険の場合、原則70歳以上の方は保険料を支払う必要がないところです。
ただし、70歳以上であっても、給付要件である保険料納付期間の10年以上を満たすために、会社に勤める場合には任意で加入できます。
参照元:厚生労働省
参照元:日本年金機構
雇用保険
自己都合で退職したときや、会社の倒産や規模縮小などにより失業してしまったときに、一定の期間給付金を受けられるのが雇用保険です。
雇用保険では、労働者の生活の安定や再就職の促進を目的としており、次の仕事が見つかるまでの“基本手当”や“失業給付”などが受け取れます。
以下2つの条件をすべて満たしている場合、雇用保険への加入が可能です。
雇用保険に加入するための条件
- 31日以上の雇用の見込みがある
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
健康保険に加入するには雇用の見込み日数が2か月必要なのに対し、雇用保険では31日以上であり、条件がやさしく設定されています。
参照元:厚生労働省
労働者災害補償保険
労働者災害補償保険(以下、労災保険)とは、労働者が業務中あるいは通勤中の事故により、怪我または死亡してしまった場合に、本人や遺族に対して給付が行われる保険です。
ほかにも、業務中に持病が悪化した場合でも、労災保険の給付対象になる可能性があります。
労災保険は、“すべての従業員”の加入が必須です。
加入するのは労働者ではなく会社側であるため、労災保険への加入について、労働者側で行う手続きや準備する書類は特にありません。
派遣会社と雇用契約を結ぶことになれば、自動的に労災保険が適用されます。
参照元:厚生労働省
派遣社員が社会保険に加入するメリット
ここまでの内容で、各保険の概要や加入条件をご理解いただけたのではないでしょうか。
条件を満たし、社会保険に無事に加入できたら、以下で紹介するメリットを得ることができます。
関連記事:好条件で働きたい!派遣スタッフが受けられる福利厚生を紹介
メリット①社会保険料の自己負担が減る
社会保険は、自営業や農林業で働く方や、どこにも勤めていない方が加入する国民健康保険と比べて保険料の自己負担額を抑えられます。
社会保険の場合、保険料の半分を勤める会社が支払ってくれます。
つまり派遣社員であれば、ご自身が登録する派遣会社が保険料の半額を負担してくれるというわけです。
一方で国民健康保険の場合は、保険料の支払いが全額自己負担です。
こうした違いから、社会保険のほうが保険料を安く済ませることができます。
ただし、それぞれ保険料の計算方法が異なるため、社会保険に加入することで、保険料が国民健康保険の半額になるわけではありません。
また社会保険の保険料は、収入やお住まいの地域によって変動します。
メリット②年金の受給額が増える
年金を多くもらえるのも、社会保険に加入するメリットの一つです。
年金制度は、建物の構造にたとえられ、“1階建て・2階建て”と表現されることがあります。
日本の公的年金制度は、20歳以上のすべての国民に加入義務がある国民年金と、会社に勤める方が加入する厚生年金保険の“2階建て構造”です。
国民年金だけに加入している場合、受け取れる年金は“老齢基礎年金”のみですが、厚生年金保険に加入していると、基礎年金に上乗せして“厚生年金”も受給できます。
派遣社員の方も給付要件を満たせば厚生年金を受けられるので、社会保険への加入が老後の安心にもつながります。
メリット③出産手当や傷病手当を受け取れる
社会保険には、被保険者の生活を保障するための制度が備わっています。
たとえば、妊娠や出産で会社を長期間休んだときの出産手当や、病気や怪我の療養で休職した際の傷病手当がこれに該当します。
これらの給付は国民健康保険では受けられないため、社会保険ならではのメリットといえるでしょう。
なお、出産手当と傷病手当では、給与の2/3程度の給付を受け取れます。
派遣社員が社会保険に加入する際の手続き
ここまでは社会保険に加入するメリットについて、お伝えしました。
加入することで、ライフステージの変化や万が一の事態に備えておけるというのは、安心につながるはずです。
ここからは、そんな社会保険に加入、または脱退する際の具体的な手続きについて解説します。
手続き自体は派遣会社側が行ってくれますが、その際に必要な書類は自身で準備することになるので、一連の流れを確認しておきましょう。
社会保険に加入するとき
派遣社員として働く場合、派遣先や労働条件の決定後に社会保険の加入手続きが行われます。
その際には、以下の3つを派遣会社に提出します。
社会保険の加入時に派遣会社へ提出するもの
- マイナンバーカード
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者番号
家族を扶養に入れる場合は、追加で以下の提出を求められる可能性もありますので、こちらも準備しておきましょう。
家族を扶養に入れる場合に提出するもの
- 住民票
- 家族のマイナンバーカード
- 配偶者の基礎年金番号
- 家族の収入証明書
加入手続きを終えて健康保険被保険者証が届くまでは、数日~数週間程度の期間を要します。
この期間内に健康保険被保険者証が必要になる可能性がある方は、事前に派遣会社に相談することをおすすめします。
社会保険を喪失するとき
登録している派遣会社を退職して次の雇用元に移るまでに、1か月以上のブランクが発生する場合には、社会保険の喪失手続きを行います。
その際は、速やかにご自身と扶養家族の健康保険被保険者証を派遣会社に返却しなければなりません。
派遣会社を退職後に、国民健康保険に加入する予定の方は、“資格喪失証明書”という書類が必要です。
この書類は派遣会社で発行してもらえるので、健康保険被保険者証を返却する際に発行を依頼しておくと、そのあとの手続きがスムーズに行えます。
また、雇用保険を喪失すると“資格喪失確認通知書”や“離職票”が交付されます。
ハローワークで失業給付を申請するときに提出を求められる書類であるため、こちらも忘れずに派遣会社に依頼しておきましょう。
なお、派遣先との契約期間が終了した場合であっても、登録している派遣会社に雇用されたままであれば、社会保険に関する手続きは必要ありません。
派遣社員が社会保険に加入する際の注意点
社会保険の加入や喪失の手続きの流れについて理解を深めたところで、以下では、派遣社員が社会保険に加入する際の注意点を2つ説明します。
派遣先ではなく派遣会社の制度を確認する
社会保険について確認したいときは、雇用元の派遣会社に問い合わせましょう。
社会保険は、派遣会社によって提供されます。
というのも、派遣社員の雇用主は、実際に業務する職場ではなく登録している派遣会社であるためです。
そのほかの福利厚生も派遣会社によって提供されるので、この点もあわせて確認しておきたいところです。
関連記事:派遣会社の選び方を解説!自分に合った派遣会社や雇用形態とは
扶養内で働きたい場合は労働時間を調整する
社会保険における扶養とは、ご自身で保険料を支払わなくとも、加入している家族の保険を自身に適用できる制度のことです。
この制度を活用するために、「扶養が適用される範囲内で働きたい」という方は、労働時間の調整が肝要です。
社会保険の扶養に入るには、一部例外を除いて、基本的に“被扶養者の年収が130万円未満”でなければなりません。
そのため、この金額を超えないように、労働時間あるいは期間を調整する必要があります。
また、あわせて気をつけたいところが、“社会保険は条件を満たした場合の加入が義務づけられている”という点です。
仮に扶養の範囲内であっても、社会保険の加入条件を満たす収入を得てしまえば、加入は必須で、扶養は適用されません。
社会保険の加入条件の一つが、“給与が月額8万8,000円以上の方”であるため、8万8,000円×12か月とすると、年収は105万6,000円と計算できます。
したがって、年収105万6,000円を超えた場合も扶養に入ることができなくなってしまうので、それを超えないように調整するのも非常に重要なポイントです。
派遣社員も条件を満たせば社会保険に加入できる!手続きの流れは派遣会社に確認を
今回は、社会保険に加入できる条件や必要な手続きについて解説しました。
派遣社員であっても、定められた条件を満たせば社会保険に加入することができます。
加入や喪失の手続きは、基本的に派遣会社が行いますが、会社によって手続きの流れが異なる可能性がありますので、詳細は所属する派遣会社に確認しましょう。
登録する派遣会社がまだ決まっていない方は、社会保険がきちんと整備されているのかどうかを基準に選ぶのもおすすめです。
ホットスタッフでは、社会保険をはじめとする充実した福利厚生を提供しております。
派遣社員一人ひとりが豊かな生活を送れるようにサポートしていますので、仕事をお探しの方はぜひお問い合わせください。